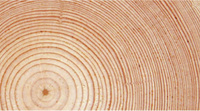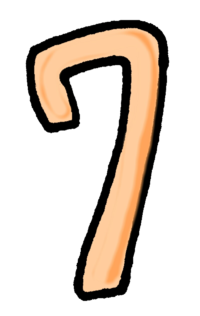2013年02月03日
ゴミの分別方法は地域によってなぜ違うのか?
こんにちは。菊池建設の sugar です。
日頃から気になっていたことや、わからないままにしていたことを解明するシリーズ(?)である「日常の世迷言」ですが、今日も以前から気になっていたことについて、お話しします。
今日のテーマは「ゴミの分別方法は地域によってなぜ違うのか?」です。
一口に分別収集と言っても、ペットボトルや紙パックに至るまで細かく分別収集するところもあれば、可燃と不燃を一緒くたにしてもOKなところもあるようで・・・。
いくら地域性があるといっても、何故同じ日本でこんなにもゴミの分別方法はバラバラなのか?
で、調べてみました。
家庭から出る一般廃棄物(いわゆるゴミ)は、市町村単位で各自治体が責任を持って分別収集、廃棄処理することになっているのはご存知のとおりです。
実はこのゴミの分別収集って、国の指針はありますが、それを受け入れて実施するか否かはそれぞれの自治体の考えに任されているのです。
そうなると自治体によって微妙に違うスタイルとなることは容易に想像がつきます。

さて、それを考える前に、そもそもゴミを分別するとどんなメリットがあるのか?考えてみましょう。
<ゴミを分別するとどういういいことがあるの?>
1 有害ゴミを誤って燃やしたり埋める心配がなくなるので、空気や土壌の汚染を防げます。
2 処理施設の焼却炉の寿命が延びます。
3 資源物をより確実に資源回収に回せるため、ゴミが減量します。
4 ゴミの減量によって、ゴミ処理に必要な費用やエネルギーを節約でき、埋立て地及び処理施設の使用期間が延びます。
5 資源物をリサイクルすると、原料となる資源や生産時に必要なエネルギーを節約できます。
というわけで、なるほどゴミの分別は意義深いものがあることは再確認できました。
ちなみに、東京では、23区は「不燃ゴミ」「可燃ゴミ」「資源ゴミ」の3分別収集が基本ですが、可燃ゴミに廃食用油や古布を入れていい区とダメな区、不燃ゴミに乾電池を入れていい区とダメな区があるなど、細かな内訳は区によって微妙に異なっています。
また、同じ東京でも多摩地区では、可燃・不燃・資源の各ゴミの他「有害ゴミ」(乾電池・スプレー缶・体温計・蛍光灯など)の区分が加わります。
各地域住民の生活レベルはさほど違わないはずなのに、これほどゴミの分別方法に違いが出てくるのには理由があります。
東京では焼却施設や最終処分場の処理の違いもありますが、それぞれの自治体のゴミの分別に対する意識や予算の違いによところが大きいのだそうです。やっぱな。
細かく分別すればするほど、中間処理などに費用がかかり、「かけたくても金がない」という自治体も出て来ているといいます。
なんだかみんなが細かく分別すれば、後で業者さんが分別をする手間が無くなるのでコストは下がると思っていましたら、実際にはまったくその真逆だったようです。
というのには、1991年の「資源利用促進法」制定が大きく関与しています。
この法律で、ビン、缶、段ボール、ペットボトル、紙パック、白色トレー(スーパーで魚や肉が入っている例のアレ)、プラスチック容器、廃家電などがリサイクル対象品に定められています。
リサイクル自体はとてもよいことなのですが、これだけの品目をすべてリサイクルしようとすればコストがかかるのは当然といえば当然ですよね。
一方、神奈川県川崎市では、現在リサイクルの対象として分別収集をしている、ビン、缶、ペットボトル、乾電池、小物金属以外は、衛生処理と埋め立て地の延命化を図るため「普通ゴミ」として全量焼却処理しています。
なお、今後分別収集をミックスペーパーや生ゴミ、その他プラスチックなどにも順次拡大する計画だとのことです。ちなみにミックスペーパーとは、「汚れた紙・臭いの強い紙」や「資源集団回収の対象物である新聞紙・雑誌・段ボール・牛乳パッ ク等」以外の全ての紙くずの事です。
確かに川崎市のようにリサイクル対象品以外の燃やせるものは全て燃やしてしまったほうがスッキリしていいような気もしますが、現実には焼却温度が高い焼却炉は非常に高価だということやダイオキシンの問題もあって、全焼却はなかなか現実的には難しいようです。

ちなみに、東京都の「不燃ゴミ」って選別した後に埋め立てられているのです。
そのためのスペースも必要なのは当然で、これも問題となっています。そんなスペースが無限にあるわけでもないですからね。
なんでもかんでも捨てるんじゃなくって使い切れるものは使い切るなど捨てる側の意識も大切ですよね。
ゴミの処理の問題は決して小さくはないですね。
(以上、 sugar こと 相川正也 でした。)
.
日頃から気になっていたことや、わからないままにしていたことを解明するシリーズ(?)である「日常の世迷言」ですが、今日も以前から気になっていたことについて、お話しします。
今日のテーマは「ゴミの分別方法は地域によってなぜ違うのか?」です。
一口に分別収集と言っても、ペットボトルや紙パックに至るまで細かく分別収集するところもあれば、可燃と不燃を一緒くたにしてもOKなところもあるようで・・・。
いくら地域性があるといっても、何故同じ日本でこんなにもゴミの分別方法はバラバラなのか?
で、調べてみました。
家庭から出る一般廃棄物(いわゆるゴミ)は、市町村単位で各自治体が責任を持って分別収集、廃棄処理することになっているのはご存知のとおりです。
実はこのゴミの分別収集って、国の指針はありますが、それを受け入れて実施するか否かはそれぞれの自治体の考えに任されているのです。
そうなると自治体によって微妙に違うスタイルとなることは容易に想像がつきます。

さて、それを考える前に、そもそもゴミを分別するとどんなメリットがあるのか?考えてみましょう。
<ゴミを分別するとどういういいことがあるの?>
1 有害ゴミを誤って燃やしたり埋める心配がなくなるので、空気や土壌の汚染を防げます。
2 処理施設の焼却炉の寿命が延びます。
3 資源物をより確実に資源回収に回せるため、ゴミが減量します。
4 ゴミの減量によって、ゴミ処理に必要な費用やエネルギーを節約でき、埋立て地及び処理施設の使用期間が延びます。
5 資源物をリサイクルすると、原料となる資源や生産時に必要なエネルギーを節約できます。
というわけで、なるほどゴミの分別は意義深いものがあることは再確認できました。
ちなみに、東京では、23区は「不燃ゴミ」「可燃ゴミ」「資源ゴミ」の3分別収集が基本ですが、可燃ゴミに廃食用油や古布を入れていい区とダメな区、不燃ゴミに乾電池を入れていい区とダメな区があるなど、細かな内訳は区によって微妙に異なっています。
また、同じ東京でも多摩地区では、可燃・不燃・資源の各ゴミの他「有害ゴミ」(乾電池・スプレー缶・体温計・蛍光灯など)の区分が加わります。
各地域住民の生活レベルはさほど違わないはずなのに、これほどゴミの分別方法に違いが出てくるのには理由があります。
東京では焼却施設や最終処分場の処理の違いもありますが、それぞれの自治体のゴミの分別に対する意識や予算の違いによところが大きいのだそうです。やっぱな。
細かく分別すればするほど、中間処理などに費用がかかり、「かけたくても金がない」という自治体も出て来ているといいます。
なんだかみんなが細かく分別すれば、後で業者さんが分別をする手間が無くなるのでコストは下がると思っていましたら、実際にはまったくその真逆だったようです。
というのには、1991年の「資源利用促進法」制定が大きく関与しています。
この法律で、ビン、缶、段ボール、ペットボトル、紙パック、白色トレー(スーパーで魚や肉が入っている例のアレ)、プラスチック容器、廃家電などがリサイクル対象品に定められています。
リサイクル自体はとてもよいことなのですが、これだけの品目をすべてリサイクルしようとすればコストがかかるのは当然といえば当然ですよね。
一方、神奈川県川崎市では、現在リサイクルの対象として分別収集をしている、ビン、缶、ペットボトル、乾電池、小物金属以外は、衛生処理と埋め立て地の延命化を図るため「普通ゴミ」として全量焼却処理しています。
なお、今後分別収集をミックスペーパーや生ゴミ、その他プラスチックなどにも順次拡大する計画だとのことです。ちなみにミックスペーパーとは、「汚れた紙・臭いの強い紙」や「資源集団回収の対象物である新聞紙・雑誌・段ボール・牛乳パッ ク等」以外の全ての紙くずの事です。
確かに川崎市のようにリサイクル対象品以外の燃やせるものは全て燃やしてしまったほうがスッキリしていいような気もしますが、現実には焼却温度が高い焼却炉は非常に高価だということやダイオキシンの問題もあって、全焼却はなかなか現実的には難しいようです。

ちなみに、東京都の「不燃ゴミ」って選別した後に埋め立てられているのです。
そのためのスペースも必要なのは当然で、これも問題となっています。そんなスペースが無限にあるわけでもないですからね。
なんでもかんでも捨てるんじゃなくって使い切れるものは使い切るなど捨てる側の意識も大切ですよね。
ゴミの処理の問題は決して小さくはないですね。
(以上、 sugar こと 相川正也 でした。)
.
Posted by スタッフブログ『ひのき同好会』 at 14:19│Comments(0)
│sugar