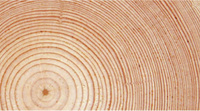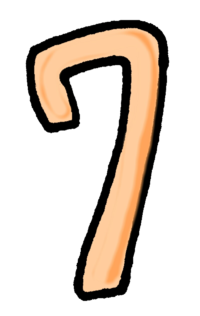2012年12月20日
なぜ第九は年末に演奏されるのか?
こんにちは。菊池建設の sugar です。
日頃から気になっていたことや、わからないままにしていたことを解明するシリーズ(?)である「日常の世迷言」ですが、今日も以前から気になっていたことについて、お話しします。
今日のテーマは「なぜ第九は年末に演奏されるのか?」です。
年末になると必ず聞こえてくるベートーベン交響曲第九番。
第4楽章の「歓喜の歌」の合唱を聴かないと年を越せないという方も多いのではないでしょうか。
さて、この第九、なぜ年の暮れに演奏されるのでしょうか。

< 年末恒例の第九 >
これも以前からずっと不思議に思っていましたが、理由を知りませんでした。
で、調べてみました。
有力な説は2つあります。
1つ目は意外や意外、第二次世界大戦中の学徒出陣が絡む話なんです。
昭和18年(1943)の学徒出陣の際、東京音楽学校(現 東京芸術大学)が壮行音楽会を開き、第九の第4楽章が演奏されました。
器楽科と声楽科の両方が参加できるというのが選曲の理由でした。
そして、終戦後の昭和22年(1947)12月30日、戦死した学生を悼む音楽会が日比谷公会堂で開かれ、再び第九が選曲されたのです。
以降も慰霊音楽会が行われ、年末の第九が定着していった・・・という説です。
なんだか感動的な話しですが、残念ながら東京芸術大学にも日比谷公会堂にもそのような演奏会があったという資料は残っていないそうなので、真偽のほどは定かではありません。
もう一つは、NHK交響楽団(N響)の前身の日本交響楽団が始めたという説です。
毎年師走に第九を演奏するようになったのは、昭和22年12月9日~13日の演奏会が最初です。
その理由の一つに、楽団員のお正月のお餅代稼ぎがあったというからこれまた驚きです。
戦後間もない頃は、楽団員は低収入で生活が苦しかったそうです。
そこで、合唱団も付く第九を演奏すれば、その家族や友人がこぞって聴きに来てくれて臨時収入になるので、年が越せる、というわけです。
その慣例がいつしか徐々に全国に広まってアマの人も演奏や合唱に参加するようになって、「年末=第九」という構図ができて来たのだという説なんです。
こちらの説の方がリアリティがあると思いませんか?
ちなみに、日本で最初に第九を演奏したのは大正7年(1918)、徳島県の収容所にいたドイツ人捕虜なんだそうです。
で、日本人の初演はというと、大正13年(1924)、「九州帝大フィルハーモニー」によるものです。
意外と歴史は浅いんですねぇ。
それから、年末に第九を演奏するのは日本だけの風習なんですって。
日本人はほんと第九が好きなんですねぇ。
(以上、 sugar こと 相川正也 でした。)
.
日頃から気になっていたことや、わからないままにしていたことを解明するシリーズ(?)である「日常の世迷言」ですが、今日も以前から気になっていたことについて、お話しします。
今日のテーマは「なぜ第九は年末に演奏されるのか?」です。
年末になると必ず聞こえてくるベートーベン交響曲第九番。
第4楽章の「歓喜の歌」の合唱を聴かないと年を越せないという方も多いのではないでしょうか。
さて、この第九、なぜ年の暮れに演奏されるのでしょうか。

< 年末恒例の第九 >
これも以前からずっと不思議に思っていましたが、理由を知りませんでした。
で、調べてみました。
有力な説は2つあります。
1つ目は意外や意外、第二次世界大戦中の学徒出陣が絡む話なんです。
昭和18年(1943)の学徒出陣の際、東京音楽学校(現 東京芸術大学)が壮行音楽会を開き、第九の第4楽章が演奏されました。
器楽科と声楽科の両方が参加できるというのが選曲の理由でした。
そして、終戦後の昭和22年(1947)12月30日、戦死した学生を悼む音楽会が日比谷公会堂で開かれ、再び第九が選曲されたのです。
以降も慰霊音楽会が行われ、年末の第九が定着していった・・・という説です。
なんだか感動的な話しですが、残念ながら東京芸術大学にも日比谷公会堂にもそのような演奏会があったという資料は残っていないそうなので、真偽のほどは定かではありません。
もう一つは、NHK交響楽団(N響)の前身の日本交響楽団が始めたという説です。
毎年師走に第九を演奏するようになったのは、昭和22年12月9日~13日の演奏会が最初です。
その理由の一つに、楽団員のお正月のお餅代稼ぎがあったというからこれまた驚きです。
戦後間もない頃は、楽団員は低収入で生活が苦しかったそうです。
そこで、合唱団も付く第九を演奏すれば、その家族や友人がこぞって聴きに来てくれて臨時収入になるので、年が越せる、というわけです。
その慣例がいつしか徐々に全国に広まってアマの人も演奏や合唱に参加するようになって、「年末=第九」という構図ができて来たのだという説なんです。
こちらの説の方がリアリティがあると思いませんか?
ちなみに、日本で最初に第九を演奏したのは大正7年(1918)、徳島県の収容所にいたドイツ人捕虜なんだそうです。
で、日本人の初演はというと、大正13年(1924)、「九州帝大フィルハーモニー」によるものです。
意外と歴史は浅いんですねぇ。
それから、年末に第九を演奏するのは日本だけの風習なんですって。
日本人はほんと第九が好きなんですねぇ。
(以上、 sugar こと 相川正也 でした。)
.
Posted by スタッフブログ『ひのき同好会』 at 17:29│Comments(0)
│sugar