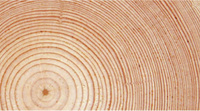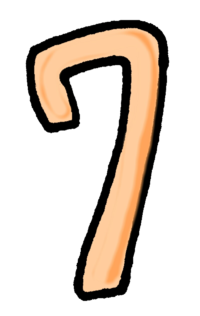2012年11月30日
道路の案内標識って?
こんにちは。菊池建設の sugar です。
日頃から気になっていたことや、わからないままにしていたことを解明するシリーズ(?)である「日常の世迷言」ですが、今日も以前から気になっていたことについて、お話しします。
今日のテーマは「道路の案内標識って?」です。
道路の案内標識には「東京23km」などと書かれているが、この場合、東京都のどこまでの距離を表示しているのでしょうか?
車を運転している時には便利な案内標識。

「11km」「26km」など、やけに半端な数字が記されているから、およその目安というよりは具体的な地点までの距離なのでしょう。
例えば、「厚木 26km」とあった場合、厚木市に足を踏み入れる地点、つまり市境まで26kmという意味なのでしょうか。
で、調べてみました。
案内標識を管轄している国土交通省に訊いてみました。
「市町村名と距離が表示されている数字は、通常、各市町村の役所の正面地点までの距離です。」(国交省 道路局 企画課)
高速道路上で「大阪 57km」と記されていたら、高速道路を降りて大阪市役所前まで主要道路を通って行った場合の距離が57kmという意味です。
ただし、「東京 ○km」に限っては、道路原点である日本橋までの距離を表示しているのだそうです。
また、街中では「日比谷 11km」「巣鴨 13km」など、市町村以外の地名が案内されている標識も見かけるけど、これはどこを基点にしているのでしょうか?
「駅などのランドマークやその地名を冠した主要交差点を基準にしています」(同 企画課)
ところで、一般道路の案内標識は「青地に白文字」、高速道路の案内標識は「緑地に白文字」だけど、表示方法も異なることを皆さんご存知でしたか?
同方向の複数地名が案内されている場合の並び順が逆なんです。
一般道路では、上を向いた矢印で現地点からの遠近感を表しているため、遠い地名ほど上(矢印の先側)になっているが、高速道路の案内標識は近い順に上から書かれているんです。
降りるインターを見逃すことがないように、近い地名を最上段にしているそうです。
(以上、 sugar こと 相川正也 でした。)
.
日頃から気になっていたことや、わからないままにしていたことを解明するシリーズ(?)である「日常の世迷言」ですが、今日も以前から気になっていたことについて、お話しします。
今日のテーマは「道路の案内標識って?」です。
道路の案内標識には「東京23km」などと書かれているが、この場合、東京都のどこまでの距離を表示しているのでしょうか?
車を運転している時には便利な案内標識。

「11km」「26km」など、やけに半端な数字が記されているから、およその目安というよりは具体的な地点までの距離なのでしょう。
例えば、「厚木 26km」とあった場合、厚木市に足を踏み入れる地点、つまり市境まで26kmという意味なのでしょうか。
で、調べてみました。
案内標識を管轄している国土交通省に訊いてみました。
「市町村名と距離が表示されている数字は、通常、各市町村の役所の正面地点までの距離です。」(国交省 道路局 企画課)
高速道路上で「大阪 57km」と記されていたら、高速道路を降りて大阪市役所前まで主要道路を通って行った場合の距離が57kmという意味です。
ただし、「東京 ○km」に限っては、道路原点である日本橋までの距離を表示しているのだそうです。
また、街中では「日比谷 11km」「巣鴨 13km」など、市町村以外の地名が案内されている標識も見かけるけど、これはどこを基点にしているのでしょうか?
「駅などのランドマークやその地名を冠した主要交差点を基準にしています」(同 企画課)
ところで、一般道路の案内標識は「青地に白文字」、高速道路の案内標識は「緑地に白文字」だけど、表示方法も異なることを皆さんご存知でしたか?
同方向の複数地名が案内されている場合の並び順が逆なんです。
一般道路では、上を向いた矢印で現地点からの遠近感を表しているため、遠い地名ほど上(矢印の先側)になっているが、高速道路の案内標識は近い順に上から書かれているんです。
降りるインターを見逃すことがないように、近い地名を最上段にしているそうです。
(以上、 sugar こと 相川正也 でした。)
.
Posted by スタッフブログ『ひのき同好会』 at 14:58│Comments(0)
│sugar