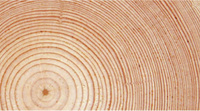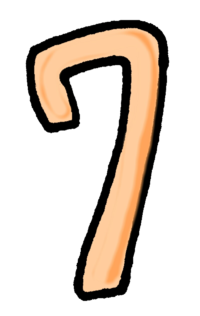2012年10月19日
ドメインってなぁに?
こんばんは。菊池建設の sugar です。
日頃から気になっていたことや、わからないままにしていたことを解明するシリーズ(?)である「日常の世迷言」ですが、今日も以前から気になっていたことについて、お話しします。
今日のテーマは「ドメインって、いったいなぁに?」です。
ホームページ(HP)やメールアドレスの末尾が「~.com」や「~.co.jp」や「~.jp」などバラバラなのは何故でしょうか?
これもずっと気にはなっていたのですが、答えを知らないままでいました。
で、調べてみました。
「jp」は私でもこれは japan の略で「日本」であることを示しているのだろうなぁ、ということは 想像がつきました。
しかし、日本の企業なのに、メールやHPに「.jp」ではなく、「.com」が使われていたり、「.co」が入ったり入っていなかったり、と一様ではないんですよね。
これは実はインターネット自体の歴史と関係があるようなのです。
もともとインターネットはアメリカの軍事用として開発され、民間に転用され始めたのが1983年ごろでした。
利用者の増加に合わせて、ネット上の各コンピューターを識別するため、<住所>にあたる「ドメイン」が導入されました。
「ドメイン」というのは、メールアドレスでは @以降の文字列、HPアドレスならばwww. 以降の文字列のことを指します。
その最後尾の部分を「トップレベルドメイン」(TLD)といい、最初のTLDとして1984年に「.com」など7種類が定められました。

ちなみに、その頃は、アメリカ国内で生まれ、アメリカ国内で使用されていたので、国の識別はなかったのです。
しかし、次第に世界規模でインターネットが普及していくに連れ、日本では1989年に、TLDに「jp」のように国別コードが導入され、会社を示す「.cojp」や政府機関を示す「go,jp」などが生まれたのです。
その後、1996年に「metro.tokyo.jp」のように自治体を表す「地域型JPドメイン」や「社名.jp」のような「汎用JPドメイン」が次々に導入されました。
ドメインの末尾がバラバラなのは、利用者が急激に増えるのに伴い、次々と新しいドメイン名が作られた結果なんだそうです。
ですから、基本的にはあまり大差はありません。
2000年にはTLDに「.biz」や「info」など、新たに7種類が追加されましたが、あまり使われていません。
こうして、「.com」「.net」「.org」などよく知られているものをはじめ、「.aero」「.arpa」「.asia」「.biz」「.cat」「.coop」「.edu」「.gov」「.info」「.int」「.jobs」「.mil」「.mobi」「.museum」「.name」「.pro」「.tel」「.travel」と合計21種類に限定されるようになりました。
さらに、2003年に導入された、日本語が使える「日本語JPドメイン」も、思った以上に普及していません。
結局、入力の手間の少ない「汎用JPドメイン」の方が人気が高いようです。
なにかしらすっごい意味があるのかと思っていましたので、かなり肩すかし感があったのは否めません。
しかし、普段何げに遣っている、メールアドレスやHPアドレスのドメインにはこんな歴史や背景があったのですねぇ。
(以上、 sugar こと 相川正也 でした。)
.
日頃から気になっていたことや、わからないままにしていたことを解明するシリーズ(?)である「日常の世迷言」ですが、今日も以前から気になっていたことについて、お話しします。
今日のテーマは「ドメインって、いったいなぁに?」です。
ホームページ(HP)やメールアドレスの末尾が「~.com」や「~.co.jp」や「~.jp」などバラバラなのは何故でしょうか?
これもずっと気にはなっていたのですが、答えを知らないままでいました。
で、調べてみました。
「jp」は私でもこれは japan の略で「日本」であることを示しているのだろうなぁ、ということは 想像がつきました。
しかし、日本の企業なのに、メールやHPに「.jp」ではなく、「.com」が使われていたり、「.co」が入ったり入っていなかったり、と一様ではないんですよね。
これは実はインターネット自体の歴史と関係があるようなのです。
もともとインターネットはアメリカの軍事用として開発され、民間に転用され始めたのが1983年ごろでした。
利用者の増加に合わせて、ネット上の各コンピューターを識別するため、<住所>にあたる「ドメイン」が導入されました。
「ドメイン」というのは、メールアドレスでは @以降の文字列、HPアドレスならばwww. 以降の文字列のことを指します。
その最後尾の部分を「トップレベルドメイン」(TLD)といい、最初のTLDとして1984年に「.com」など7種類が定められました。

ちなみに、その頃は、アメリカ国内で生まれ、アメリカ国内で使用されていたので、国の識別はなかったのです。
しかし、次第に世界規模でインターネットが普及していくに連れ、日本では1989年に、TLDに「jp」のように国別コードが導入され、会社を示す「.cojp」や政府機関を示す「go,jp」などが生まれたのです。
その後、1996年に「metro.tokyo.jp」のように自治体を表す「地域型JPドメイン」や「社名.jp」のような「汎用JPドメイン」が次々に導入されました。
ドメインの末尾がバラバラなのは、利用者が急激に増えるのに伴い、次々と新しいドメイン名が作られた結果なんだそうです。
ですから、基本的にはあまり大差はありません。
2000年にはTLDに「.biz」や「info」など、新たに7種類が追加されましたが、あまり使われていません。
こうして、「.com」「.net」「.org」などよく知られているものをはじめ、「.aero」「.arpa」「.asia」「.biz」「.cat」「.coop」「.edu」「.gov」「.info」「.int」「.jobs」「.mil」「.mobi」「.museum」「.name」「.pro」「.tel」「.travel」と合計21種類に限定されるようになりました。
さらに、2003年に導入された、日本語が使える「日本語JPドメイン」も、思った以上に普及していません。
結局、入力の手間の少ない「汎用JPドメイン」の方が人気が高いようです。
なにかしらすっごい意味があるのかと思っていましたので、かなり肩すかし感があったのは否めません。
しかし、普段何げに遣っている、メールアドレスやHPアドレスのドメインにはこんな歴史や背景があったのですねぇ。
(以上、 sugar こと 相川正也 でした。)
.
Posted by スタッフブログ『ひのき同好会』 at 14:41│Comments(2)
│sugar
この記事へのコメント
な~るほど!ありがとうございます!一つ賢くなりました(^o^)/
Posted by ♪ 音楽小僧 ♫ at 2012年10月20日 09:20
at 2012年10月20日 09:20
 at 2012年10月20日 09:20
at 2012年10月20日 09:20>音楽小僧 ♫ 様
ご高覧、ありがとうございます。
また、遊びに来てくださいね。
.
ご高覧、ありがとうございます。
また、遊びに来てくださいね。
.
Posted by sugar at 2012年10月20日 16:34