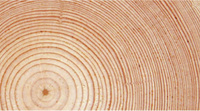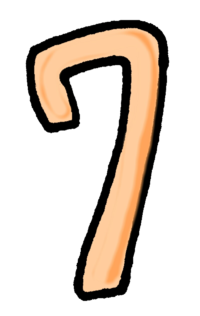2012年09月25日
ビールの大ビン
こんにちは。 菊池建設の sugar です。
日頃から気になっていたことや、わからないままにしていたことを解明するシリーズ(?)である「日常の世迷言」ですが、今日も以前から気になっていたことについて、お話しします。
以前から、ビールを飲むたびに気になっていたことがありました。
それは、「ビールの大ビンの容量は何故、633mlなのか?」 ということです。
缶ビールは、350mlや500mlと、まずまずピッタリした数字なので納得できるのですが、大ビンは633mlなんですよ。
何故、こんな中途半端な数字なのでしょうか?

< 一番好きなサッポロ黒生 >
調べてみました。
実はこの量に決まったのは戦前の酒税法の影響なのだと言います。
昭和15(1940)年に新しい酒税法が制定され、それを機にビールの容量を統一することになったのです。
それまでは、会社ごとに違ったばかりか、同じ会社でも出荷する工場ごとに容量はバラバラでした。
後にアサヒビールとサッポロビールに分かれることになる前身の「大日本麦酒」と、「麒麟麦酒」の2社、計14工場で使われていたビンの容量を見てみると、3.57合(約644ml)から3.51合(約633ml)までまちまちでした。
当時はかなりいい加減だったんですねぇ。
しかし、戦前はガラスビンは貴重品でした。
容量を統一するためにビンを新調する余裕はとてもなかったわけです。
そこで、容量が一番小さなモノに合わせよう!ということになったんですね。
容量が一番小さなモノに合わせれば、大きめのビンでも対応できたからです。
そのため、昭和19(1944)年に3.51合=633mlに決められたのです。
ちなみに、小ビンが、334mlとやはり中途半端なのも、これと同じ理由です。
これでようやく解決! かと思ったのですが・・・
そうなると次に疑問になってくるのが中ビンの存在でした。
何故、同じビンビールなのに中ビンだけが500mlとピッタリした容量なのか?
実は中ビンの誕生は他のビンよりも遅くて、昭和32(1957)年で、当時大ビン1本が125円だった時に「宝酒造」が500mlの中ビンを100円ちょうどという買いやすい価格の「タカラビール」を売り出しました。
これが買いやすいという理由で大ヒットとなり、他社も追随して中ビン=500mlが定着したというわけです。
ほんと、なんにでも理由っていうものがあるんですねぇ。
さぁー、帰ってビール飲も!
(以上、 sugar こと 相川正也 でした。)
.
日頃から気になっていたことや、わからないままにしていたことを解明するシリーズ(?)である「日常の世迷言」ですが、今日も以前から気になっていたことについて、お話しします。
以前から、ビールを飲むたびに気になっていたことがありました。
それは、「ビールの大ビンの容量は何故、633mlなのか?」 ということです。
缶ビールは、350mlや500mlと、まずまずピッタリした数字なので納得できるのですが、大ビンは633mlなんですよ。
何故、こんな中途半端な数字なのでしょうか?

< 一番好きなサッポロ黒生 >
調べてみました。
実はこの量に決まったのは戦前の酒税法の影響なのだと言います。
昭和15(1940)年に新しい酒税法が制定され、それを機にビールの容量を統一することになったのです。
それまでは、会社ごとに違ったばかりか、同じ会社でも出荷する工場ごとに容量はバラバラでした。
後にアサヒビールとサッポロビールに分かれることになる前身の「大日本麦酒」と、「麒麟麦酒」の2社、計14工場で使われていたビンの容量を見てみると、3.57合(約644ml)から3.51合(約633ml)までまちまちでした。
当時はかなりいい加減だったんですねぇ。
しかし、戦前はガラスビンは貴重品でした。
容量を統一するためにビンを新調する余裕はとてもなかったわけです。
そこで、容量が一番小さなモノに合わせよう!ということになったんですね。
容量が一番小さなモノに合わせれば、大きめのビンでも対応できたからです。
そのため、昭和19(1944)年に3.51合=633mlに決められたのです。
ちなみに、小ビンが、334mlとやはり中途半端なのも、これと同じ理由です。
これでようやく解決! かと思ったのですが・・・
そうなると次に疑問になってくるのが中ビンの存在でした。
何故、同じビンビールなのに中ビンだけが500mlとピッタリした容量なのか?
実は中ビンの誕生は他のビンよりも遅くて、昭和32(1957)年で、当時大ビン1本が125円だった時に「宝酒造」が500mlの中ビンを100円ちょうどという買いやすい価格の「タカラビール」を売り出しました。
これが買いやすいという理由で大ヒットとなり、他社も追随して中ビン=500mlが定着したというわけです。
ほんと、なんにでも理由っていうものがあるんですねぇ。
さぁー、帰ってビール飲も!
(以上、 sugar こと 相川正也 でした。)
.
Posted by スタッフブログ『ひのき同好会』 at 23:47│Comments(1)
│sugar
この記事へのコメント
これってブログ??
なんかつまんないですネッ! インターネットみれば全部分かるし…
なんかつまんないですネッ! インターネットみれば全部分かるし…
Posted by ★テルキ★ at 2012年09月26日 11:24