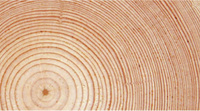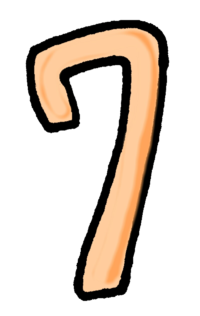2012年06月23日
襖(ふすま)
こんにちは。 菊池建設の sugar です。
今日は、「襖(ふすま)」を取り上げてみたいと思います。

< 襖(ふすま) >
そもそも「襖(ふすま)」とは今から約1200年前の西暦800年代つまり平安時代に、日本独自のものとして生まれた間仕切り建具です。
元々は几帳(きちょう)、衝立(ついたて)、屏風(びょうぶ)、あかり障子など、「寝殿造り」の内部の調度品から発生してきたものなのです。
昔は、「襖」は「障子」という言葉で表されてきました。というより、「障子」の中に「襖障子」と「明かり障子(いわゆる現在の障子)」が含まれていたのです。
それが「明かり障子」だけを指す言葉として「障子」が、「襖障子」を指す言葉として「襖」が、次第に一般に浸透していったようです。
ご承知のように、「襖」は主に引き戸として使われています。
引き戸ですから、敷居と鴨居にはめ込んでスライドさせるだけという具合に構造が単純な上、 枠材と襖紙と引き手だけで構成されているので、デザイン的にもシンプルな建具です。
材料的にも、一部引き手で金属が使われることがありますが、その主体は木と紙で作られていますので、エコな建具でもあります。
最近では、住宅の洋風化が進み、ともすると和室のない家まで登場しているので、「襖」の存在も忘れられがちではありますが、機能性とデザイン性を兼ね備えた建具ですので、見直す価値は充分にあると思います。
以前はふすま紙には、松の木などが描かれていることが多かったのですが、最近は基本的には無地が好まれ、少し繊維が混ざった材質のものが人気が高いようです。

< 葛布(くずふ) > ※ 葛の繊維を紡いだ糸からつくられる織物のこと。
同じ襖でも、ふすま紙の代わりに「葛布(くずふ)」を貼ったり、写真のようにふすま紙を千鳥に貼る(色の濃い紙と薄めの色の紙を互い違いに貼ること)などして、あなたなりのセンスでお洒落な「襖」を再考してみませんか?
ちなみに、葛布は静岡県掛川市産のものが質がよくて、人気がありますよ。
少々お高いですが・・・
(以上、 sugar こと 相川正也 でした。)
.
今日は、「襖(ふすま)」を取り上げてみたいと思います。

< 襖(ふすま) >
そもそも「襖(ふすま)」とは今から約1200年前の西暦800年代つまり平安時代に、日本独自のものとして生まれた間仕切り建具です。
元々は几帳(きちょう)、衝立(ついたて)、屏風(びょうぶ)、あかり障子など、「寝殿造り」の内部の調度品から発生してきたものなのです。
昔は、「襖」は「障子」という言葉で表されてきました。というより、「障子」の中に「襖障子」と「明かり障子(いわゆる現在の障子)」が含まれていたのです。
それが「明かり障子」だけを指す言葉として「障子」が、「襖障子」を指す言葉として「襖」が、次第に一般に浸透していったようです。
ご承知のように、「襖」は主に引き戸として使われています。
引き戸ですから、敷居と鴨居にはめ込んでスライドさせるだけという具合に構造が単純な上、 枠材と襖紙と引き手だけで構成されているので、デザイン的にもシンプルな建具です。
材料的にも、一部引き手で金属が使われることがありますが、その主体は木と紙で作られていますので、エコな建具でもあります。
最近では、住宅の洋風化が進み、ともすると和室のない家まで登場しているので、「襖」の存在も忘れられがちではありますが、機能性とデザイン性を兼ね備えた建具ですので、見直す価値は充分にあると思います。
以前はふすま紙には、松の木などが描かれていることが多かったのですが、最近は基本的には無地が好まれ、少し繊維が混ざった材質のものが人気が高いようです。

< 葛布(くずふ) > ※ 葛の繊維を紡いだ糸からつくられる織物のこと。
同じ襖でも、ふすま紙の代わりに「葛布(くずふ)」を貼ったり、写真のようにふすま紙を千鳥に貼る(色の濃い紙と薄めの色の紙を互い違いに貼ること)などして、あなたなりのセンスでお洒落な「襖」を再考してみませんか?
ちなみに、葛布は静岡県掛川市産のものが質がよくて、人気がありますよ。
少々お高いですが・・・
(以上、 sugar こと 相川正也 でした。)
.
Posted by スタッフブログ『ひのき同好会』 at 16:12│Comments(0)
│sugar