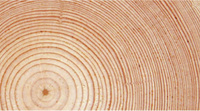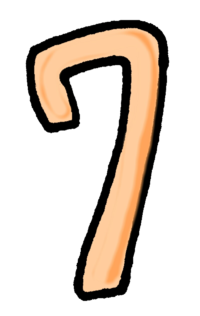2012年03月03日
☓とはいったい・・・
こんにちは。菊池建設の sugar です。
今日は昨日の続きです。
昨日、〇というマークについて、お話ししましたので、今日は一方の☓について考えてみたいと思います。

<知る人ぞ知る、☓の大家・ブッチー武者! by 「オレたち ひょうきん族!」>
バツという言い方ですが、これは起源が日本語かどうかもよくわからないのです。
ただ、日本では昔「都合」と書いて『バツ』と読んでいたそうです。
今でも「都合が悪い」ということを「バツが悪い」なんて言い方をしたりしますものね。
さて、この☓の2本の線はそもそも「道」を表していて、それが交差している状態を☓というマークで表しています。
『辻』という言葉がありますが、この『辻』という字の中の「十」は数字の10という意味ではなくて、道のクロスポイントである☓から来ているというんですね。
だから、道と道が出会うところ、交錯するところ、つまり交差点が『辻』となるわけです。
「辻斬り」なんていうのは、道を歩いていて、この道が交わる角のところで別の方角からいきなり出て来た「賊」に出会い頭にそれも不意打ちで斬られちゃうわけですから、逃げようがないわけです。
さて、先に述べた「バツが悪い」のバツは、その場の具合のことで、すなわち辻褄(つじつま)の意味です。
ここでも☓が関係してきます。
辻褄の『辻』は道が出会う十字路でしたね。
『褄』もまた、着物の裾の左右が出会うところです。
したがって、「辻褄が合う」とは、左右がうまく合うこと、転じて、事態や事情の符牒がうまく合うことを言うわけです。
これは道理がうまく通ったという意味にもなります。
これらのことから考えますと、本来☓には〇もそうだったように、肯定の意味も否定の意味もないことがわかります。
また、☓のそれぞれの先端は都につながり、都と都を結ぶ街道の交差点が☓になったとも考えられます。
つまり、二つ以上の世界が出会うという、非常に大切な意味をも含んでいるのです。
☓の起源については諸説ありますが、おそらくメソポタミアあたりで生まれたのではないか、と言われています。
それが、西洋に渡って+(プラス)となり、東洋に伝わって卍(まんじ)となったのだろうと推察されています。
ですから、☓の発生は西洋と東洋の中間あたりだと想像できるのです。
たぶん、カスピ海、黒海、ペルシア湾を結ぶ三角地帯のあたりではないか?とも言われています。
この辺は、その昔はゾロアスター教やミトラ教が熱心に信仰された地域と重なります。
西へ行った☓は立ち上がって+(クロス)となり、聖十字となり、東へ行った☓は回転して卍になったわけです。
☓が+と卍と仲間だったなんて・・・ 「実に面白いっ!」(福山雅治風に)
さて、☓の東方神秘主義が「回転」を重視したことは。古代インドのシンボリズムの中で「車輪」が多用された事実にも共通した考え方があるように思えます。
「回る」ことは、「輪廻」を暗示し、つまりそれは「再生」をも示唆します。
ひいては「永遠」や「不死」というイメージにもつながっていくのです。
当時の人々はそれを願い、憧れてそういうシンボルを多用したわけです。
とまぁ、こうして☓もまた、世界に広がって行ったのですねぇ~。
昨日のブログで〇についても言いましたが、☓もまた〇と同じように元々の意味においては、肯定や否定の意味を持っていなくって、単なる形態のシンボルだったと考えられています。
では、☓はどうして否定の意味合いで使われるようになったのでしょうか?
☓は単なる目印として使われることもありますよね。
事故現場などで車が衝突した地点にチョークで☓と描いたりします。
また、宝地図では宝のありかを示しています。
また、人や動物につける目印としても☓は使われます。
というのも、そもそも入れ墨というのは、額に☓と印をつけるところから始まったのだというんです。
古代中国では、生まれたばかりの赤ん坊の額や胸、腹にやはり☓印をつけたのだそうです。
(理由はわかりませんが、たぶんその子の明るい将来を願って、悪しきモノから守るという魔除け的な意味合いがあったのだと思います。)
このように、思いはそうでも☓が結果的に体を傷つけてしまうということから、否定的な意味合いが生じてきたのではないか・・・と類推されます。
余談ですが、「文」という漢字も、☓から発生したものです。
また、入れ墨のことを「文身」という言い方もあります。
「文」という字には「印をつける」という意味があるのです。
文章を書くというのもまた、紙の上に印を残す作業に他なりません。
☓は不思議な力を持つマークと考えられ、目印としても使われるようになっていったのです。
そして、そこから発展して「チェックする」という意味も持つようになって来るのです。
こうして見てみると、〇も☓も今の様な意味(肯定や否定の意)に使われるまでには、それぞれいろいろあったのだということがわかります。
普段、何げなく使っている〇と☓ ・・・
これらのマークにも紆余曲折の歴史が隠れていたのですねぇ。
う~ん、ロマンだなぁ・・・
(以上、 sugar こと 相川正也 でした。)
.
今日は昨日の続きです。
昨日、〇というマークについて、お話ししましたので、今日は一方の☓について考えてみたいと思います。

<知る人ぞ知る、☓の大家・ブッチー武者! by 「オレたち ひょうきん族!」>
バツという言い方ですが、これは起源が日本語かどうかもよくわからないのです。
ただ、日本では昔「都合」と書いて『バツ』と読んでいたそうです。
今でも「都合が悪い」ということを「バツが悪い」なんて言い方をしたりしますものね。
さて、この☓の2本の線はそもそも「道」を表していて、それが交差している状態を☓というマークで表しています。
『辻』という言葉がありますが、この『辻』という字の中の「十」は数字の10という意味ではなくて、道のクロスポイントである☓から来ているというんですね。
だから、道と道が出会うところ、交錯するところ、つまり交差点が『辻』となるわけです。
「辻斬り」なんていうのは、道を歩いていて、この道が交わる角のところで別の方角からいきなり出て来た「賊」に出会い頭にそれも不意打ちで斬られちゃうわけですから、逃げようがないわけです。
さて、先に述べた「バツが悪い」のバツは、その場の具合のことで、すなわち辻褄(つじつま)の意味です。
ここでも☓が関係してきます。
辻褄の『辻』は道が出会う十字路でしたね。
『褄』もまた、着物の裾の左右が出会うところです。
したがって、「辻褄が合う」とは、左右がうまく合うこと、転じて、事態や事情の符牒がうまく合うことを言うわけです。
これは道理がうまく通ったという意味にもなります。
これらのことから考えますと、本来☓には〇もそうだったように、肯定の意味も否定の意味もないことがわかります。
また、☓のそれぞれの先端は都につながり、都と都を結ぶ街道の交差点が☓になったとも考えられます。
つまり、二つ以上の世界が出会うという、非常に大切な意味をも含んでいるのです。
☓の起源については諸説ありますが、おそらくメソポタミアあたりで生まれたのではないか、と言われています。
それが、西洋に渡って+(プラス)となり、東洋に伝わって卍(まんじ)となったのだろうと推察されています。
ですから、☓の発生は西洋と東洋の中間あたりだと想像できるのです。
たぶん、カスピ海、黒海、ペルシア湾を結ぶ三角地帯のあたりではないか?とも言われています。
この辺は、その昔はゾロアスター教やミトラ教が熱心に信仰された地域と重なります。
西へ行った☓は立ち上がって+(クロス)となり、聖十字となり、東へ行った☓は回転して卍になったわけです。
☓が+と卍と仲間だったなんて・・・ 「実に面白いっ!」(福山雅治風に)
さて、☓の東方神秘主義が「回転」を重視したことは。古代インドのシンボリズムの中で「車輪」が多用された事実にも共通した考え方があるように思えます。
「回る」ことは、「輪廻」を暗示し、つまりそれは「再生」をも示唆します。
ひいては「永遠」や「不死」というイメージにもつながっていくのです。
当時の人々はそれを願い、憧れてそういうシンボルを多用したわけです。
とまぁ、こうして☓もまた、世界に広がって行ったのですねぇ~。
昨日のブログで〇についても言いましたが、☓もまた〇と同じように元々の意味においては、肯定や否定の意味を持っていなくって、単なる形態のシンボルだったと考えられています。
では、☓はどうして否定の意味合いで使われるようになったのでしょうか?
☓は単なる目印として使われることもありますよね。
事故現場などで車が衝突した地点にチョークで☓と描いたりします。
また、宝地図では宝のありかを示しています。
また、人や動物につける目印としても☓は使われます。
というのも、そもそも入れ墨というのは、額に☓と印をつけるところから始まったのだというんです。
古代中国では、生まれたばかりの赤ん坊の額や胸、腹にやはり☓印をつけたのだそうです。
(理由はわかりませんが、たぶんその子の明るい将来を願って、悪しきモノから守るという魔除け的な意味合いがあったのだと思います。)
このように、思いはそうでも☓が結果的に体を傷つけてしまうということから、否定的な意味合いが生じてきたのではないか・・・と類推されます。
余談ですが、「文」という漢字も、☓から発生したものです。
また、入れ墨のことを「文身」という言い方もあります。
「文」という字には「印をつける」という意味があるのです。
文章を書くというのもまた、紙の上に印を残す作業に他なりません。
☓は不思議な力を持つマークと考えられ、目印としても使われるようになっていったのです。
そして、そこから発展して「チェックする」という意味も持つようになって来るのです。
こうして見てみると、〇も☓も今の様な意味(肯定や否定の意)に使われるまでには、それぞれいろいろあったのだということがわかります。
普段、何げなく使っている〇と☓ ・・・
これらのマークにも紆余曲折の歴史が隠れていたのですねぇ。
う~ん、ロマンだなぁ・・・
(以上、 sugar こと 相川正也 でした。)
.
Posted by スタッフブログ『ひのき同好会』 at 12:30│Comments(0)
│sugar