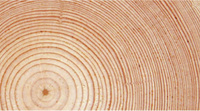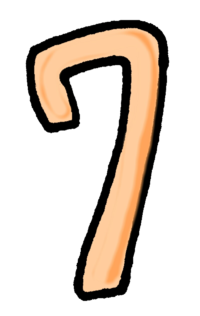2011年09月15日
建築探訪 ~「法隆寺(ほうりゅうじ)」その2
こんにちは! 菊池建設の sugar こと、相川正也です!
日本中の建築物の中から「おっ!これはっ!」というモノを紹介する建築探訪の第三回目は、 前回に引き続き、奈良の「法隆寺(ほうりゅうじ)」を取り上げてみたいと思います。
前回の「建築探訪」では、法隆寺は再建されたのか?建立当時からの建物なのか?についてご紹介しました。
今日は、少し視点を変えて、法隆寺の中でも一際目を引く、「五重塔」についてご紹介します。

【「五重塔」全景】
この法隆寺の「五重塔」は、現存する日本最古の塔であるとともに、木造としてはなんと世界最古の塔でもあり、その威風堂々とした姿には感銘を受けます。
一番下の初重(しょじゅう)は3間四方、1辺が6.41mで、その高さは32.5mという高さを誇ります。
今の高層ビルに換算すると約11階建てのビルとほぼ同じ高さですから、およそ1400年前に建てられたことを考えると相当なものです。
塔の中心に建てられている「心柱(しんばしら)」は、当初地下3mほどに心礎(しんそ)と呼ばれる大きな石を据えて、その上に「掘っ立て柱」のように立っています。
この心礎の下には、穴が掘られていてその中には、お椀型の「椀」という容器があり、その中に銅製の「合子(ごうし)」というカプセル型の容器があり、さらにその中に金と銀の透かし彫りを施した二重の卵型容器があり、さらにその中にガラス製の舎利瓶(しゃりびん)が鎮座しています。そして、その中には釈迦の遺骨である「舎利(しゃり)」が納められていると伝えられています。
当時、大切な大切なお釈迦様の遺骨は、ロシアの入れ子人形マトリョーシカのように幾重にも厳重なほどに包まれて納めていたのですね。
さて、心柱に話を戻しますが、この心柱は途中で継いではいますが、1本の通し柱となって五重の屋根の上に10mもの高さで空にそびえる「相輪(そうりん)」という部分を支えています。

【相輪】
その他の柱は各層ごとに立てられていて、通し柱はありません。
塔自体は、下の層の屋根の上に上の層を積み重ね、それを繰り返すことによって、5層部分が組み上げられているのですが、心柱とは構造上、まったく切り離されているのです。

【五重塔 構造図】
実は、この約1400年という気が遠くなるほどの長き間において、この「五重塔」が地震で倒れたという記述はありません。
この地震に対しての強さには、どんな秘密があるのでしょうか?
この「五重塔」の耐震性については・・・
① 「五重塔」は32.5mもの高さがあるので、塔本体の固有の揺れである「固有周期」が長く、地震の時の地盤の短い揺れの周波とは違うため、共振することがほとんどないと考えられる。
② 木造のため、多くの木の部材から構成されているので、それらが地震時にお互いこすり合って、揺れのエネルギーを吸収しあうと考えられる。
③ 木が組み合わさった箇所で互いにずれて、変形が大きくなり、全体としては大きく揺れても壊れるまでには至らないと考えられる。
④ 「心柱」が振動を軽減する閂(かんぬき)の役目を果たしていると考えられる。
⑤ 現代の、地震で揺れないようガッチリ構造を固めて、地震力に打ち勝つという耐震の考え方とは異なり、木造特有の「しなやかさ」を武器に、いわば柳の木のようなイメージで、敢えて少しだけ揺れさせて地震力を分散軽減させるという今の免震と制震の考え方を先駆的に取り入れた構造であると考えられる。
・・・との理由が挙げられています。
いずれにしても、1400年前の当時の大工さん達がこのように地震に強い塔を造り上げ、世界最古の木造の塔として現代まで残してくれたっていうコトは、すごい技術であるとは思いませんか?
これが、当時の大工さん達が、そこまで見越して設計そして施工していたとしたら・・・それは、とてつもないコトだと思います。
それは真実かどうかは今となってはわかりませんが・・・
もしかして、UFOから降り立った宇宙人が、このすごい木造技術を教えてくれたのかもしれません。www
当時の職人さんたちに敬意を表するとともに、木造建築の懐の深さに魅了されてしまうのです。
ここにもまたロマンがありました。
ではまた。
日本中の建築物の中から「おっ!これはっ!」というモノを紹介する建築探訪の第三回目は、 前回に引き続き、奈良の「法隆寺(ほうりゅうじ)」を取り上げてみたいと思います。
前回の「建築探訪」では、法隆寺は再建されたのか?建立当時からの建物なのか?についてご紹介しました。
今日は、少し視点を変えて、法隆寺の中でも一際目を引く、「五重塔」についてご紹介します。

【「五重塔」全景】
この法隆寺の「五重塔」は、現存する日本最古の塔であるとともに、木造としてはなんと世界最古の塔でもあり、その威風堂々とした姿には感銘を受けます。
一番下の初重(しょじゅう)は3間四方、1辺が6.41mで、その高さは32.5mという高さを誇ります。
今の高層ビルに換算すると約11階建てのビルとほぼ同じ高さですから、およそ1400年前に建てられたことを考えると相当なものです。
塔の中心に建てられている「心柱(しんばしら)」は、当初地下3mほどに心礎(しんそ)と呼ばれる大きな石を据えて、その上に「掘っ立て柱」のように立っています。
この心礎の下には、穴が掘られていてその中には、お椀型の「椀」という容器があり、その中に銅製の「合子(ごうし)」というカプセル型の容器があり、さらにその中に金と銀の透かし彫りを施した二重の卵型容器があり、さらにその中にガラス製の舎利瓶(しゃりびん)が鎮座しています。そして、その中には釈迦の遺骨である「舎利(しゃり)」が納められていると伝えられています。
当時、大切な大切なお釈迦様の遺骨は、ロシアの入れ子人形マトリョーシカのように幾重にも厳重なほどに包まれて納めていたのですね。
さて、心柱に話を戻しますが、この心柱は途中で継いではいますが、1本の通し柱となって五重の屋根の上に10mもの高さで空にそびえる「相輪(そうりん)」という部分を支えています。

【相輪】
その他の柱は各層ごとに立てられていて、通し柱はありません。
塔自体は、下の層の屋根の上に上の層を積み重ね、それを繰り返すことによって、5層部分が組み上げられているのですが、心柱とは構造上、まったく切り離されているのです。

【五重塔 構造図】
実は、この約1400年という気が遠くなるほどの長き間において、この「五重塔」が地震で倒れたという記述はありません。
この地震に対しての強さには、どんな秘密があるのでしょうか?
この「五重塔」の耐震性については・・・
① 「五重塔」は32.5mもの高さがあるので、塔本体の固有の揺れである「固有周期」が長く、地震の時の地盤の短い揺れの周波とは違うため、共振することがほとんどないと考えられる。
② 木造のため、多くの木の部材から構成されているので、それらが地震時にお互いこすり合って、揺れのエネルギーを吸収しあうと考えられる。
③ 木が組み合わさった箇所で互いにずれて、変形が大きくなり、全体としては大きく揺れても壊れるまでには至らないと考えられる。
④ 「心柱」が振動を軽減する閂(かんぬき)の役目を果たしていると考えられる。
⑤ 現代の、地震で揺れないようガッチリ構造を固めて、地震力に打ち勝つという耐震の考え方とは異なり、木造特有の「しなやかさ」を武器に、いわば柳の木のようなイメージで、敢えて少しだけ揺れさせて地震力を分散軽減させるという今の免震と制震の考え方を先駆的に取り入れた構造であると考えられる。
・・・との理由が挙げられています。
いずれにしても、1400年前の当時の大工さん達がこのように地震に強い塔を造り上げ、世界最古の木造の塔として現代まで残してくれたっていうコトは、すごい技術であるとは思いませんか?
これが、当時の大工さん達が、そこまで見越して設計そして施工していたとしたら・・・それは、とてつもないコトだと思います。
それは真実かどうかは今となってはわかりませんが・・・
もしかして、UFOから降り立った宇宙人が、このすごい木造技術を教えてくれたのかもしれません。www
当時の職人さんたちに敬意を表するとともに、木造建築の懐の深さに魅了されてしまうのです。
ここにもまたロマンがありました。
ではまた。
Posted by スタッフブログ『ひのき同好会』 at 22:55│Comments(0)
│sugar