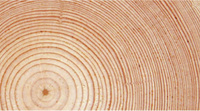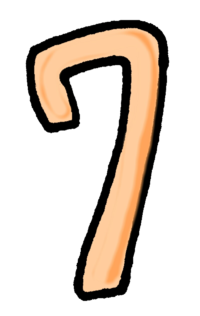2014年08月03日
寿司と鮨
こんにちは。菊池建設の sugar です。
日頃から気になっていたことや、わからないままにしていたことを解明するシリーズ(?)である「日常の世迷言」ですが、今日も以前から気になっていたことについて、お話しします。
で、今日のお話しは「寿司と鮨」です。

一昔前までは高級な食品の代表だった「お寿司」ですが、最近は手頃な価格で食べることのできる「回転寿司」があちこちにオープンしてより身近な食べ物になったようです。
ところで、この「回転寿司」を漢字で書くときにあまり「回転鮨」とは書きませんね。
ご承知のように、「すし」には「寿司」と「鮨」と二通りの漢字が存在します。
いったいどのように使い分けるのでしょうか?
気になったので調べてみました。
もともとの「すし」の語源を尋ねると、「酸っぱいもの」という意味を表す「酸(す)し」または「酢(す)し」であるというのが定説です。
古くは「すし」とは、魚介類を塩蔵して自然発酵させたものやさらに飯を加えて発酵を促したもの、つまりは「熟れ鮨(なれずし)」のことでした。
それが江戸時代になって、ご飯に酢を混ぜて作られる「すし」が登場しました。
以来、漢字で書くときには酢飯に魚の切り身を乗せて職人が握ったり、型枠に入れて作るものを「鮨(すし)」と表すようになったと言われています。
「鮨」・・・「魚」偏に「旨い」と書くとは、いかにも「すし」らしい漢字ですよね。
あまりにもピッタリしていて、これは当て字ではないかと思われる向きもいるでしょうが、実は当て字なのは「寿司」の方なのです。
昔からめでたい席で食されることが多かったので、「寿(ことぶき)を司(つかさど)る」と、縁起を担いで「寿司」と当てはめられたのです。
ですから、出自の違いはありますが、意味的には「鮨」も「寿司」も厳密な区別はないので、どちらを使っても基本的にはOKです。
ですが、サラダ巻きやアボガド巻きのような新種のものや「お稲荷さん」などは「鮨」という字よりも「寿司」の方がしっくりくるようです。
そして、職人さんの技が光る握りは「鮨」の方がいかにもネタが新鮮で美味しそうに感じます。
日常でも「握り鮨」とは書いても「握り寿司」とはまず書きません。
我々は肌で感じて、微妙な使い分けをしているようです。
あーぁ、たまには美味しいお鮨、食べたくなっちゃった・・・
(以上、 sugar こと 相川正也 でした。)
.
日頃から気になっていたことや、わからないままにしていたことを解明するシリーズ(?)である「日常の世迷言」ですが、今日も以前から気になっていたことについて、お話しします。
で、今日のお話しは「寿司と鮨」です。

一昔前までは高級な食品の代表だった「お寿司」ですが、最近は手頃な価格で食べることのできる「回転寿司」があちこちにオープンしてより身近な食べ物になったようです。
ところで、この「回転寿司」を漢字で書くときにあまり「回転鮨」とは書きませんね。
ご承知のように、「すし」には「寿司」と「鮨」と二通りの漢字が存在します。
いったいどのように使い分けるのでしょうか?
気になったので調べてみました。
もともとの「すし」の語源を尋ねると、「酸っぱいもの」という意味を表す「酸(す)し」または「酢(す)し」であるというのが定説です。
古くは「すし」とは、魚介類を塩蔵して自然発酵させたものやさらに飯を加えて発酵を促したもの、つまりは「熟れ鮨(なれずし)」のことでした。
それが江戸時代になって、ご飯に酢を混ぜて作られる「すし」が登場しました。
以来、漢字で書くときには酢飯に魚の切り身を乗せて職人が握ったり、型枠に入れて作るものを「鮨(すし)」と表すようになったと言われています。
「鮨」・・・「魚」偏に「旨い」と書くとは、いかにも「すし」らしい漢字ですよね。
あまりにもピッタリしていて、これは当て字ではないかと思われる向きもいるでしょうが、実は当て字なのは「寿司」の方なのです。
昔からめでたい席で食されることが多かったので、「寿(ことぶき)を司(つかさど)る」と、縁起を担いで「寿司」と当てはめられたのです。
ですから、出自の違いはありますが、意味的には「鮨」も「寿司」も厳密な区別はないので、どちらを使っても基本的にはOKです。
ですが、サラダ巻きやアボガド巻きのような新種のものや「お稲荷さん」などは「鮨」という字よりも「寿司」の方がしっくりくるようです。
そして、職人さんの技が光る握りは「鮨」の方がいかにもネタが新鮮で美味しそうに感じます。
日常でも「握り鮨」とは書いても「握り寿司」とはまず書きません。
我々は肌で感じて、微妙な使い分けをしているようです。
あーぁ、たまには美味しいお鮨、食べたくなっちゃった・・・
(以上、 sugar こと 相川正也 でした。)
.
Posted by スタッフブログ『ひのき同好会』 at 09:03│Comments(0)
│sugar